~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
裁判員制度はいらないインコのウェヴ大運動
トピックス
押し黙る4万6千人、守秘義務死守は何を意味するのか
インコは常々、疑問に思っています。この国の政府・最高裁はどうしてここまで厳しい縛りをかけたのか…。裁判員法はなぜこれほど厳しい守秘義務を国民に課したのだろうかと。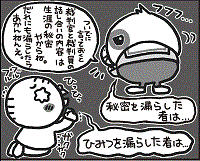
この制度は国民に義務を課す制度なのだからみんなが裁判の内容を話題にすることなど想定しなかったのだろうというのが一般的な見方なのだそうです。しかし考えてみれば、みんなに話題にして貰った方が制度の趣旨がより早く広く国民の間に伝わり、より多くの国民がこの制度に親しみを感じてくれるはずですよね。この国の司法が正統に行われてきたとみんなが声を上げても悪くはない。広く知られないようにしようとかできるだけ秘密にしようというような発想はこの制度に不可欠・不可避のルールでもないように思います。
裁判員法が定める守秘義務の内容を簡単におさらいしておくと…。裁判員や補充裁判員が評議の秘密のほか職務をしている間に知った秘密を漏らすと「秘密漏示罪」という名前の犯罪が成立するのです。刑罰は6か月以下の懲役か50万円以下の罰金。裁判員や補充裁判員の職務に従っている時に犯せばもちろんですが、職務が終わってから漏らしてもこの犯罪が成立します。裁判官や裁判員の評議中の意見はこうだったと言ったり、このような意見を言った人が何人いたなどと言っただけで犯罪が成立するのです。また、本当はこのように認定すべきだったと思うとかこのような量刑にすべきだったと思うなどと言ったり、言い渡された判決の事実認定や量刑のよしあしについて意見を述べただけで犯罪になります。その判断でよかったと思うと言っだだけでも成立するという恐ろしい法律です(裁判員 秘密漏らして 被告人)。
これで、何も言わない、何も書かない、ひたすら黙るという究極の沈黙の世界が現出しています。脅された裁判員たちの多くは、自分は恐ろしい世界に足を突っ込んでしまった(突っ込まされてしまった)ものよという感覚に陥ります。また、裁判員たちの周囲の人々も裁判員たちにものを聞いてはいけないらしいという腫れ物に触るような心境に追い込まれているのです。
朝日新聞ニューヨーク支局の中井大助記者が米国で陪審員を務めた経験報告を書いた文章(昨年12月6日の紙面記事と25日の「記者有論」欄)を読んで、あらためてこの思いを深くしました。
中井記者は、陪審員を務めた経験で「司法参加の原点」を実感したと言います。市内で男性2人の背中を刺して怪我をさせたという傷害事件。弁護側は捜査のずさんさなどをいろいろ指摘しました。実際、証言はあいまいで調書の信用性も争われましたが、1人については、結局「怪我を負わせた場合」の2級傷害罪の成立で全員一致。もう1人については「重大な怪我を負わせる意図」をめぐって争われ(その意図があれば1級傷害未遂が成立し、なければ無罪)、陪審員の間で意見が割れたが、1日半の評議でこちらは無罪になった。中井記者は2つの事件でともに少数派だったということです(陪審制は全員一致制のため、記者も最後にはほかの意見に同調したという)。
中井記者は、「被告人と同じ立場にある市民として」「全員同意して」結論を出すところに陪審制度の根幹があると評価しつつ、現実の運用を考えると刑事裁判のあり方として陪審制が最善なのか疑問が大きくなったと結んでいます。また、「ここで経験したことをぜひ話してほしい。それでこそ制度が広く理解されるから」という裁判官の言葉に感銘を受け、日本の裁判員裁判の「守秘義務」をもっと緩めて、裁判員制度に関する議論がより活発に交わされることも提言しています。
日本で裁判員制度の取材をした経験を持つ中井記者が、米国の裁判官から「陪審員としての経験を広く知らせてほしい」と求められて感銘を受けたのは、日本の裁判員制度の強烈な秘密主義と陪審制の公開精神の落差を感じたからでしょう。米国では、有名な陪審事件の陪審員手記が店頭に並ぶことが珍しくありません。陪審裁判の問題点もいろいろ取りざたされていますが、陪審裁判に対する裁判官の誇りと陪審制の歴史の重みに一線記者として衝撃を受けたことは想像に難くない(記者が陪審制にも懸念を感じた理由についても知りたいところですが、それはここではとりあえず措いておきます)。
さて、問題は裁判員制度。わが国の「司法参加」制度に不抜の確信があるのなら、国も最高裁も、この制度のもとで行われる評議の過程や量刑の論議について、国民の間であらゆる角度から自由闊達に議論してほしいと言ってもよかったでしょう。どうしてそのような態度をとらなかったのか。
これまでに4万6千人もの国民が裁判員や補充裁判員として法壇に坐り、6500人近い被告人が彼らが参加した裁判で裁かれています。しかし、そこで裁判員たちが本当は何を感じ、何を評価し、何を批判しているのかということは霧の中、いえ闇の中です。裁判所が裁判官の面前で裁判員たちに書かせるアンケートでも、各地の裁判所で開かれている意見交換会の場でも、裁判官に対する遠慮や守秘義務の縛りが拘束になって真実はほとんど明らかにされていない(意見交換会の発言記録にも「守秘義務の制約があるのでこれ以上は言えない」などという弁解が出てきている)。最高裁の報告書は、アンケートや意見交換会の結果を引いて制度の定着を自賛していますが、これで真実がわかったという人は少ないでしょう。
最高裁は、3年後の見直しでも守秘義務の緩和にはまったく手を付けませんでした。守秘義務の死守の陰にあるのは、この制度の真実が国民に知らされることへの底知れぬ恐怖ではないでしょうか。守秘義務の緩和は日弁連などが繰り返し求めていることですが、義務を緩和すればこの制度がよくなるのではなく(裁判員たちの参加が刑事裁判の基本を破壊していることが満天下に明らかになるだけで)、これほどまで厳格な守秘義務を課しても堅持しようとしているところに、この制度の基本的な問題性が象徴的に示されていると思います。
投稿:2014年1月12日