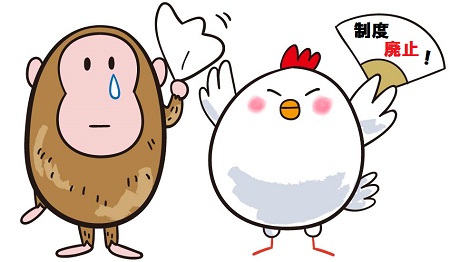~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
裁判員制度はいらないインコのウェヴ大運動
トピックス
投稿ージャカルタ事件と裁判員裁判
弁護士 川村 理
私は、2016年9月21日から11月24日にかけて、通称「ジャカルタ事件」の裁判員裁判を担当した(第1審の主任弁護人)。
もともと私は、裁判員制度反対論であり、裁判員裁判を積極的に担うことを予定していなかったが、果たしてこれを担当してみると、予想どおり、裁判員裁判は、被告人・弁護人の防御権を大きく後退させ、裁判員の都合ばかりを優先させるとんでもない代物だった。
私の担当した事件は、いわゆる公安事件であり、罪名は、殺人未遂罪と偽造有印公文書行使罪であった。ちなみに、その事件の発生は1986年5月という今から約30年前である。被告人は、事件につき無実であると主張したが、検察官は懲役15年を求刑し、判決は懲役12年の有罪実刑判決であった。
以下、この裁判の幾多の問題点の中から、特に裁判員裁判特有のおかしさを中心に、私が経験した事実のうち、公表して差し支えない部分を報告しておきたい。
<公判前整理手続き>
本件の公判請求(起訴)は、2015年の3月13日(殺人未遂)と同年4月3日(虚偽公文書偽造)の2回に分けて行われた。
前者の起訴罪名は裁判員対象事件であったため、本件は、公判請求後直ちに公判前整理手続きに付された。裁判員対象事件である以上、現行法上、この手続きを回避することはできない。
その後の公判前整理手続きは、2015年10月23日から2016年9月1日まで、合計15回実施された(被告人はいずれも出頭)。また、それ以外の法曹三者による進行協議期日は、合計13回行われた。
公判前整理手続きと言えば、それにより証拠開示の範囲が拡大されるから、被告弁護側に有利な面が多いと指摘する制度推進派の弁護士がいる。
しかしながら、自身の体験に基づけば、かかる評価は間違いである。
本件においては、検察官の請求証拠、開示証拠は併せて約900点程あり、確かに大量の証拠が開示されたため、コピーに要する費用や手間が大変なほどであった。しかしながら、これら大量の開示証拠のうち、弁護側の立証として実際に活用できるものはごくごく僅かなものでしかなかった。
また、これら大量の開示証拠も、一度に全部が開示となるのではなく、極めて五月雨式に、そろりそろりと開示されるのであり、この点では従来の検察の手口にはなんら変わりがなかった。このような証拠開示制度を積極的に評価することはとてもできない。
さて、従来、本件のような公安事件においては、「大衆的裁判闘争」という言葉もあるように、弁護団、被告人の闘いを傍聴人(支援者)が支援し、裁判の現状を広く社会にも訴えることにより、「主戦場を法廷の外」におき、社会に裁判の不当性を訴える中でその勝機を探っていくという手法が一般的であった。
しかしながら、公判前整理手続きは、それが非公開であるから、この種の戦術に持ち込むことが非常に困難となる。傍聴席に誰もいない静かな法廷に、被告人・弁護人は時に孤立感すらを感じたものだ。なお、本件において、弁護人は公判前整理手続きの公開を裁判所に対し求めたこともあったが、全く歯牙にもかけられなかった。
また、公判前整理手続きにおいては、被告人の主張や立証を公判開始前に明示する必要があり、それを行わない限り、後の弁護側の立証には制限を受けることになる。ことに本件の場合、被告人は事件当時は他国にいたというアリバイの主張をしたため、ある程度の主張の事前明示が避けられず、このような現状は、そもそも被告の黙秘権行使との関係で大いに疑問がある。さらに、弁護人は、被告人のアリバイを示すための証人も用意したが、この証人の証言内容についても、公判前に概要を明らかにせよとの制度まで存在する。
つまり公判前整理手続きの現実は、公判前に被告・弁護側の主張立証を裸にして検察官の前に晒すことなのである。検察・警察は、豊富な人的物量を用いて公判前にこれを潰しにかかってくることはもちろんだ。
なお、こうした公判前整理手続きの結果、本件公判は、後述のとおり、約21期日が予定され、10分単位で細かくスケジュールが組まれた。
<裁判員の選任手続き>
本件における裁判員の選任手続きは、2016年9月5日に実施された。
裁判員候補者の総数は220名あったのに対し、当日の出席は40名(当日の辞退希望は8名)であった。
その結果、本件の裁判員候補者の出頭率は約18%ということになり、最近の平均出頭率が約23%であることに対するとやや低い数値ということになるが、本件公判が後述のとおり合計21回もの多数開廷を要するものであったことを考えると、この数字の評価は微妙である。
<地獄の連日的開廷>
本件では、9月21日の初公判から11月1日の最終弁論に至るまで、概ね週4開廷のペースにて20回の期日(午前10時から午後5時までが基本)が実施された。そして11月24日に,21回目の期日が実施され,判決が言い渡された。いわゆる連日的開廷の強行である。
元東京地裁所長である池田修氏の書物「解説 裁判員法」によれば、長期にわたる事案においては、連日的開廷といえども週3日程度の進行が適当であるかのように書かれてあるが、昨今の東京地裁の実務では、これ以上の公判ペースが組まれる現状にある。
そして本件でも、週4日を基本とする公判予定が組まれ、弁護人の反対によるも、結局この公判日程で押し切られた。
ところで、連日的開廷は、民間人たる弁護士にとっては、まさに地獄のような手続きである。開廷の最中、基本的に弁護士は他の事件が一切できないことは勿論、開廷前約1ヶ月あたりから事前準備のためにやはり他の事件をこなす余裕はなくなってくる。連日的開廷は、従来の裁判のように基本的には次回期日の準備を・・・という準備のあり方ではとうてい立ち向かえないのであり、冒頭陳述の準備から証拠のまとめ、尋問事項の準備など多くの項目を同時的に準備することに迫られるためだ。従って、私の場合、開廷前の1ヶ月は本件のみに集中する日々となった。
そして、本件のように「20回越え」の審理になると、連日的開廷の最中に気力・体力を持たせることも大変にしんどい。個人の資質もあろうが、私の場合は、始まって1週間で目にクマができ、2週間目以降は疲労から知能が低下して簡単な言葉の言い違えをするようになった。
また、連日的開廷はそれが終わると今度は急に暇になる。これは、私が連日的開廷が開始される前にその他の事件を都合を終結させるなどの措置を執ったため、瞬間的に手持ち案件が皆無に等しい状況を呈したためである。私の場合、業務が通常の状況に戻るのに、裁判終結後、約1ヶ月を要した
結果、私は、本件の連日的開廷により、その前後を含めた合計3ヶ月間、他の事件に携わることができない状態となってしまった。定額の給与が保証されている公務員や高額の弁護士報酬を得られる案件であればいざ知らず、本件のように連日的開廷が長期化すれば、担当弁護士の生活にも本格的な危機をもたらすのである。
更に、公判前整理手続きによって予定を整理した連日的開廷は、そもそも「訴訟は水物」と言われる裁判の本質に合致しない。訴訟の最中に予期しない突発的な出来事が生じ、それに対する対応が必要な場合でも、事前に立てた公判予定との関係でこれをどうするか、という事態にしばしば陥り、場合によっては、予期せぬ出来事への対応力が落ちてくる。これは、民間人たる弁護側において、特に顕著であり、これにきちんと対応しようとすれば、多額の資金を用いて多くの弁護人を確保する必要が出てこよう。が、多くの被告人はその資金を有しないであろう。
連日的開廷は、裁判員に負担をかけないためと称して、裁判員裁判において本格導入されたものであるが、明らかに被告・弁護側に不利でしかない、とんでもない制度である。もともと「戦車と竹槍」に比較される検察と弁護との力関係をさらに拡大しているのだ。
<法廷の警備>
本件は、いわゆる過激派の事件であり、工藤会の「裁判員声かけ事件」の直後に実施された案件でもあるためか、法廷の警備は極めて厳重に実施され、多数の法廷警備員が配置につき、傍聴人の所持品検査はボディタッチを含む厳格な形態で実施された。また、傍聴人の出入り口には、「裁判員に接触することを禁止し、仮に裁判員に威迫や請託をすれば処罰する」旨の注意書きが大書されていた。
<法廷通訳問題>
本件は、証人尋問に関する法廷通訳に多くの問題があるとして報道され、最後は読売新聞が2016年11月29日の社説で問題を取り上げた。
具体的には、特定の通訳人の翻訳に「約200カ所の誤訳」があるとされ、裁判所はその正確性を検証するために鑑定を実施したというものである。
この問題につき、ここでは3点の問題点を指摘しておきたい。
まず、法廷通訳の問題は、従来から指摘されてきたにもかかわらず、これに抜本的な解決を見ないまま今日に至っているということ。
本件誤訳問題は、本件が、長期事案であるがゆえに、たまたま鑑定という対応が可能になったに過ぎず、3日や5日で終わるという一般の裁判員裁判では問題が看過されていた可能性が強い。つまり、多くの事案では、誤訳問題が気付かれずに埋もれている可能性がある。
また、担当弁護人としては、上記通訳鑑定に対しても、本来は緻密な対応が必要と言えたが、連日的開廷に起因する各種問題ゆえに、これに対する十分な対応がなしえなかったという反省がある。
<判決の評価>
前記のとおり、被告人に対しては懲役12年の有罪実刑判決が言い渡された。そもそも、本件被告人は、事件への関与を完全に否定していたのであり、この主張が受け入れられなかったことについて、担当弁護人としては、憤りの気持ちで一杯である。
しかしながら、事実認定の問題については、今後の控訴審手続きもあるため、ここでは触れず、判決の量刑判断の問題について一言述べておきたい。
本件は、検察の求刑が15年であったのに対し、判決は12年であったから、いわゆる8掛けということになり、従来の実務からも、本件は、相場通りの結果であったともいうこともできよう。
しかしながら、判決文の量刑理由の中身を読むと、ここに裁判員裁判の特質がよく出ていた。なんと、この判決は、被告人に対する死刑や無期懲役の可能性を検討していたのである。
本件は、求刑15年の事案であるし、死者が一人も出ていない事件であるから、本来なら、死刑や無期懲役が問題となることはありえない。しかしながら、本判決は、最終的にそれが否定されたにせよ、評議ではこれが一旦は問題とされたからこそ、その部分が判決文にも載っているのであろう。裁判員裁判の厳罰化はこのようなところにも顔を覗かせているのだ。
<裁判員の記者会見の問題>
判決後、例によって、裁判員による記者会見が行われた。
記者会見の中身は、報道でしか知らないが、おやおやと思った裁判員の感想を1点指摘しておく。
それは23歳の女性裁判員が、「自分が生まれる前の事件だったのでよく調べて審理に臨んだ」とコメントした点である。
そもそも裁判員は、その選任の際、法廷で取り調べられた以外の証拠で認定判断をしてはならぬ旨、裁判長から注意を受けている。にもかかわらず、この女性裁判員は、法廷外で自ら調べたことを頭に入れ、それを念頭に評議に臨んだ可能性がある。最近の朝日新聞の「裁判員物語」にも似たような裁判員の私的調査の出来事が美談のように書いてあったが、実は法廷外の出来事から心証を取るというのはとんでもないルール違反だ。
私がたまたま体験したに過ぎない一つの裁判員裁判でもこのようなことがあるのだから、似たような事象(例えば、裁判員が、被告人の名前をネット検索して情報を集め、それに基づいて心証を形成していくなど)は、全国の裁判員裁判で頻発している可能性がありそうだ。
<小括>
色々と裁判の経験から感じた問題を並べてみたが、考えてみれば、このような問題点はいくつもの裁判員制度反対運動がかねてから指摘していたことばかりである。私としても、実際の裁判員裁判の経験で得られた新たな発見(制度の問題点という意味で)はほとんどなく、「裁判員裁判でまともな弁護ができない」ことを改めて痛感したというばかりである。
現在、国民の多くは裁判員候補者として動員されることを拒絶しており、大きく見れば、裁判員制度はすでに崩壊的危機に瀕していることが明らかだ。しかしながら、制度は形式上は生きている。したがって、制度の被害者ともいうべき被告人、弁護人は、今も不当な闘いを強いられている。
このことに想いを致し、今後も裁判員制度に反対の声を強めていこうと思う。
また、機会があれば、本件についての補足報告をするかもしれませんが、その節はよろしくお願いいたします。
投稿:2016年12月31日