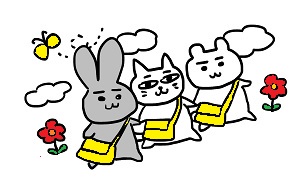~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
裁判員制度はいらないインコのウェヴ大運動
トピックス
「裁判員のあたまの中」はたいがいヘンである(後編)
裁判員制度はいらないインコ
マネージャーが『裁判員のあたまの中』というインコとしては正直読みたくない本の内容をまとめた文章を持ってきた。それが(前編)である。インコは、最初の元裁判員の感想を読んだだけでぐしゃっと潰してゴミ箱に放り込みそうになった(本当はゴミ箱に一度は捨てた。けれどマネージャーの怖さを思い出し、そっと拾い出した)。マネージャーからこのまとめに対する感想を書くように言われていたのだった。![]()
インコはくちばしを食いしばって読んだ。それはそうしなければどうしても読めない代物だった。
読者のみなさんは、(前編)を読まれてどのように思われただろうか。インコは本当はそれが一番知りたい。裁判員候補者の出頭率が激減している中で、「それでもボクは裁判員をやりたい」という「居残り組」というのは一体どんな人たちなのか。インコは、「人を裁いてみたくて仕方ない人、ヘンなことにやたら好奇心を持つ人、国の言うことには無条件で従う人」になっているのではと思っていたが、その予想は完全に当たっていた。いや、当たっていたなんてもんじゃない、あまりにも当たりすぎていて、そら恐ろしい感じがして…
「人を裁くことに対する恐れの気持ち」がまるでない人たちがここにいる。そして裁判という国家の大事に実際に関わっている。多くは好奇心やゲーム感覚で人を裁いている。人の人生を左右することを楽しんでいるかのようだ。死刑事件でもタダでもやりたいとか、お金を払ってでもやってみたいという人がいる。達成感があったという人、ひとつやってやろうじゃないかと思う人もいる。選ばれて心中「ふふふっ」と笑った人もいる。こんな人たちが裁判員になることを最高裁は予定していたのだろうか。竹崎長官の言う「定着」とはこういう状況を指すのか。![]()
「自分も家族も変わった。家族の会話に犯罪や裁判のことが加わった」と喜ぶ人の言葉を読んで、そうなるだろうと最高検察庁の幹部が言っていたのを思い出した。「昨日までの自分とは変わる」と最高裁や法務省が出した新聞全面広告も思い出した。しかし、そういう元裁判員が「事件がフラッシュバックして調子が悪く、サポート窓口も対応してくれない」と言っている。自分が傷ついているのである。だがこの人はその自分が被害者だとは思っていない。「死を直視することに慣れておく教育が必要。そうしておかないとPTSDになってしまう」と言うのだから。どうして自分たちがそんなことをしなければならないのかという疑問を持たない不思議。「国が決めたこと」にひたすら従い、自ら傷つきながらも制度を受け入れる世紀末的異様さ。
死刑判決に関わった人の中には、被告人に黙秘権を認めることに疑問を持ち、自分たちの判断に不満を言ったり控訴したりすることを批判する人もいる。たぶん、この人たちは黙秘権の意味をまったく理解していないだろう。国連人権委員会から「死刑判決は必ず上訴審の判断を仰ぐことにせよ」と求められていることももちろん知らないだろう。 そこにあるのは、自分たちの判断が疑いの目で見られたり、不服を主張されたりしたくないという不遜な思いだけだ。
もっとも、数少ない元裁判員だが、「裁判員に負担を追わせるのはいかがか」とか「またやる自信はない」とか「裁判官の出来レースに乗せられていた」というような感想や意見を述べる人がいる。このような企画本の中にもそういう声が登場してくるところにこの制度の問題性が滲み出ている。
この本に登場してくるほとんどの人たちは「破れかぶれの逆版ヘンリー・フォンダ」ばかり。考えてみればこの本を出した「現代人文社」は、『裁判員裁判を楽しもう』という本を出して顰蹙を買った出版社。こういう人たちがいればこういう出版社もあるという組み合わせの妙。![]()
ほとんどの国民が裁判員になるのを嫌がっている。だれもが気にしているそのことにこの人たちが一言も触れないのはなぜだろうか。この本の編著者がそのような感想や意見をすべてカットしたのかもしれないが、どちらにしても不可解。多くの読者が一番知りたかったところはそのあたりだったのではないか。
とにかく、これはヘンな人たちによる、ヘンな人たちのための、ヘンな本である。
投稿:2014年3月22日